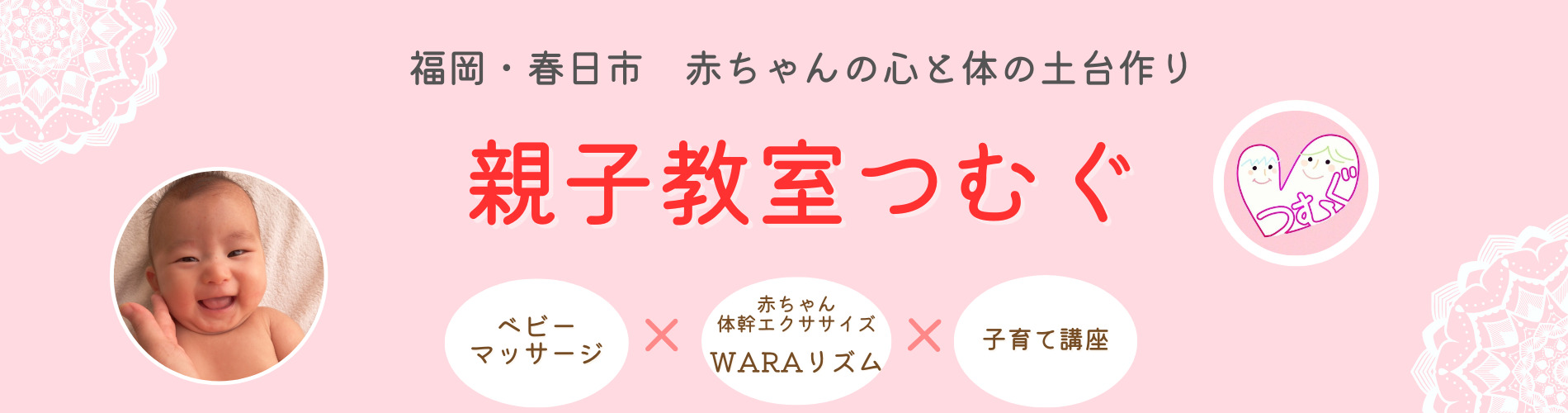ママ逹からの質問。
「なかなか寝ないんだけど、どうしたらいいのかな?」
「同じ方向しか向かないけど頭の形大丈夫?」
「おっぱいを片方しか飲んでくれない」
「抱っこを嫌がるんだけど、やり方が悪い?」
「日中ずっと機嫌が悪くて何もできない」
に対して、要因の1つに『向き癖』があることを前々回ブログで書きました。そして、向き癖があることで生じる影響についても前回書いています。
→抱っこ、授乳、頭の形、寝ない···気になる子育ての悩み、実は同じ要因が関係している!?
→「赤ちゃんの頭の形が心配…。」実は頭の変形だけではない向き癖の影響について
向き癖、できることならつけたくないですよね。ではどうしたら向き癖を予防、対策できるのか。
それを考えるのにまずは『向き癖って何でつくの!?』から考えたいと思います。
『つむぐ』の投稿は私が学んだり、経験したことのおすそ分け。
書いた通りにするといいよ~ではなくて、自分たちの生活に合っているな、チャレンジしてみようかな、必要だなというところを取り入れて自分達親子だけの子育ち、親育ちを模索してみてください♪
向き癖ってなんでつくの⁉実は産まれる前からついていることも。
向き癖がつく要因は1つではありません。まずは妊娠中、出産時も要因の1つとして考えられます。それぞれに説明していきますね。
妊娠中から
赤ちゃんの向き癖は、実は産まれる前からついていることもあります。お腹の中にいる時に同じ方向ばかり向いていた赤ちゃんは、産まれてからも同じ方向を向くことが多いようです。
これには子宮環境が影響しています。本来ふんわりとまるい子宮の中で赤ちゃんは丸まった姿勢を取っています。そして体内にいる間に手足をなめたり、足を曲げ伸ばししたり、グルンと回ってみたりいろいろな動きをしています。
ところが子宮環境が狭く、細長い状態だと赤ちゃんの体は足が伸びきっていたり、背骨がまっすぐだったりします。丸まるスペースがない、動き回れない。そんな環境で頭もずっと固定されていると向き癖がついてしまうこともあります。子宮環境って大事ですね。妊娠中から・・・もっと言ったら妊娠前から体を整えることが大事です。

お産の時
お産はママも赤ちゃんも大仕事。双方にそれなりの負荷がかかります。赤ちゃんが出てくる時、特に頭や首に強い捻りや圧迫、引っ張る力が加わると首の骨が歪んだり、頭の形が変形することもあり、それが向き癖へとつながることもあります。
これからの対策のヒントになる『生活・姿勢』による要因
このブログをお読みの方は、大半が出産後の方だと思います。ですので、特に今後の対策のヒントとなる『生活・姿勢』による要因について詳しくお伝えします。

生活、姿勢
・いつも同じ方向に寝かせている
・添い寝でお母さんが寝る位置が決まっている
・抱っこは決まって右側で
・ぐずらない限り寝かせたまま
など、こんな生活をしていませんか?
赤ちゃんは光や音に反応します。明るい方を向こうとするし、声が聞こえたらそちらが気になります。例えば、壁側に寝ていたとしたら壁をじっと見るより、家族の声が聞こえたり、明るい方に興味がわきます。
ましてや赤ちゃんはママパパが大好きです。大好きなママパパがいるなら、なおさらそちらを向きたくなりますよね。
寝る時も、ママパパの匂いや心音を感じていると安心して眠ることができます。よって、ずっと同じ方向に寝ている、同じ方向に抱っこしていると、自然と同じ方ばかりを向くようになります。
赤ちゃんの頭蓋骨は出産のときに狭い産道を通るため、柔らかく変形しやすい状態になっています。ですので同じ状態がずっと続くと頭の形が変形し、そのことで余計に向き癖が付きやすくなります。
また、赤ちゃんは産まれてすぐは自分の体の感覚がぼんやりしています。
最初、赤ちゃんが自分の体と認識しているのは、おっぱいやミルクを飲む唇くらいだとも言われています。
たまたま手が口に当たり、それを口の中に入れてしゃぶってみる。そうすることで口で感じる感覚と、手で感じる感覚を知り、視覚からも手を確認して、だんだんこれが自分の手だと認識していきます。
このように赤ちゃんが自分の体を知る、ボディイメージを育てるためには、刺激を受ける、感覚を知るということは欠かせません。
もし、刺激が一方向からだと同じ方向ばかり向くことだけではなく、ボディイメージの左右差や捻れが生じ、向き癖に繋がることもあります。
向き癖の要因から対策を考える
『なぜ向き癖がつくのか⁉』について読んでいただきました。では向き癖の対策としてどんなことが効果的なのか・・・少し見えてきたのではないでしょうか。
産まれてすぐの赤ちゃんは自分で環境を変えることはできません。ですので、私たち大人が生活・姿勢について振り返ってみてくださいね。上記に挙げたような生活していませんでしたか?
次回は具体的な対策について書いていきます。